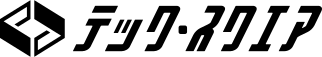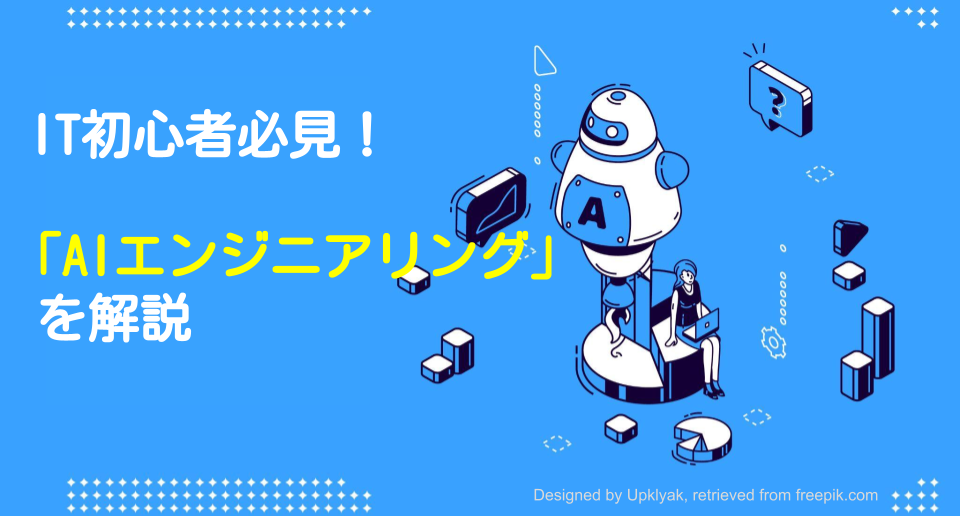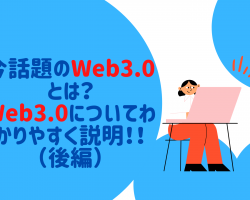Gartner社が発表した「2022年の戦略的テクノロジのトップ・トレンド」
今後ビジネス業界のスタンダードとなり得るトレンドをまとめたランキングを抜粋し、前回記事では「分散型エンタープライズ」の解説を行いました。
早くもシリーズ第5弾を迎えた今回は、同じくトレンドにランクインした「AIエンジニアリング」を取り挙げてみることにしました。
「AI」に紐づくトレンドワードを扱うのは、本シリーズでは2記事目となります。
IT業界のトレンド記事を執筆し始めてからは、徐々に素人の筆者にも「AI」の何たるかが分かってきたような気がしますが、今回のテーマは【AI×エンジニアリング】。
AIエンジニアリングとは何を指す言葉なのか、そして今後のビジネス業界においてどのような価値を生み出すものなのか。
筆者なりに学び、筆者の解釈としてまとめて来ましたので是非ご一読ください!
目次
AIエンジニアリング 10秒まとめ
- AIエンジニアリングとは、AIモデルを継続的に運用していくためのアプローチ。
- 継続的なAIモデルの開発と実装を推進していくためには、AI開発技術の向上、開発とユーザーの連携、データ収集・管理体制の確立が不可欠。
AIエンジニアリングとは
Gartner自身がAIエンジニアリングの意味するところを詳しく解説してくれている訳ではないため、現状手に入る情報を整理しながら筆者なりに定義を探ってみました。
もはや本シリーズでは恒例となりつつありますが、AIエンジニアリングという言葉を解釈するには、まずAIとエンジニアリングの意味をそれぞれ理解する必要がありそうです。
まず、日本語で「人工知能」と呼ばれるAI (Artificial Intelligence) は、知覚や思考をはじめとする人間の振る舞い (知能) をコンピュータ上に再現する技術のことを指します。
言い換えるならば、AIとは「条件付きでヒトの理性的な認知や意思決定、行動をコンピューターに再現させる技術」とも表現できるでしょう。
AIについては、同じくGartnerのトレンドにランクインした「ジェネレーティブAI」の解説記事で詳しくお話ししましたので、気になる方はぜひ一度過去記事をご確認ください。
では、続いて「エンジニアリング」という言葉の意味を考えてみます。
私たちが耳慣れている「エンジニア」は機会や電気に関する専門的な知識・スキルを持った技術者を指す言葉ですが、「エンジニアリング」とは自然科学の知見に基づいて有形・無形のプロダクトを設計・構築する学問/分野を指します。
つまるところ「AIエンジニアリング」とは、何らかの知見に基づいて、AIモデルの構築や活用を推進していくためのアプローチのことであると推測できます。
ブラジルの多国籍企業 Stefanini Groupは、「アルゴリズムやニューラル・ネットワーク、プログラミングといった要素をAIアプリケーションの開発に役立てる」ことがAIエンジニアリングであると解説しています。
AI活用の限界
ここまでで、「AIエンジニアリング」は一つの学問領域として確立されてはいるものの、過去記事で取り上げてきたような具体性のあるソリューションやツール・サービスとは違い、非常に抽象的なトレンドであることが見えてきました。
ところで、なぜGartnerはわざわざ概念的なトレンドを打ち出しているのでしょうか。
どうやらその背景には、ビジネス界隈、テクノロジー界隈におけるAIプロジェクトの孤立があったようです。
Gartnerによれば、人工知能 (AI) プロジェクトのプロトタイプから本稼働に至ったケースは、全体の53%ほどに過ぎません。
また、単独のアプリケーションとしてはAIを実装できたとしても、それらがビジネスにおいて継続的に、またAI以外の技術とともに活用されるようになるまでには、まだまだ長い道のりがあるのです。
AI活用推進に向けた3つの取り組み
では、AIエンジニアリングという枠組みの中でAIの実用化を加速させていくためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。
AIエンジニアリングに関するさまざまな資料に目を通してみると、ビジネス業界におけるAIの活用促進には以下のようなアプローチが不可欠だということがわかります。
- AI開発が現在直面している技術的な課題を解決する。
- AI開発に携わるエンジニア自身が、ビジネスへの理解を深める。
- AIモデルの学習対象となるデータの収集・管理体制を確立する。
①技術的な課題の解消
現在までに実装されてきたAIモデルの多くは、何かひとつのタスクを処理することに長けた特化型AIがほとんどです。
既存のAIモデルが活躍できる領域が限定的である一方、海外のIT系メディア IT Chronicleは、 ビジネスプロセスにおいて特定の1地点だけで動作するのではなく、経営戦略の策定から顧客管理までのさまざまなタスクをこなせるAIが必要だと指摘しています。
このような汎用型のAIを開発していくには、コンピューター科学とデータ処理、AI技術に関する専門的な知見・スキルを併せ持ったAIエンジニアの育成、延いてはエンジニア育成の基盤と教材を充実させることが不可欠です。
②開発現場と経営・業務の連携
新規性のみを追求して新たなAIモデルを構築しても、それが実際にビジネスの現場で何らかの価値を発揮しなければ意味がありません。
活用方法のみえないAIの開発ばかりが先行し、プロダクトができてしまってから既存のビジネススキームに無理やり落とし込もうとするのには強引でしょう。
同じくIT Chronicleによれば、用途のないAI開発を防ぐには、開発側とユーザー側の綿密なコミュニケーションが不可欠だといいます。
開発に携わるエンジニア自身がビジネスへの理解を深めたり、AIモデルを採用する経営・業務の最前線に立つ人材の課題やニーズを知見として蓄えながら、リリース後も継続して活用し続けられるAIを開発していくことが求められているのです。
③学習用データの確保
構築したAIモデルを継続的に活用し続けていくためには、AIによる判断・行動の精度を高めていく必要がありますが、そのために必要なのが十分な規模の教師データです。
実際に、Gartnerが約600社を対象に実施したアンケート調査では、ビジネスにおけるAIの実装を阻む要因として学習データの量的・質的不足や複雑性などが挙げられました。
ヒトの振る舞いを人工知能に再現させる時には実際に稼働させるまでに十分な学習期間を設けるのが一般的ですが、学習用の教師データに量と質に不足があるとAIの処理精度は低くなってしまいます。
例として、大量の画像の中から「リンゴのイラスト」を含むものだけを抽出してくれるAIモデルを想像してみます。
「リンゴのイラスト」がどのようなものなのかをAIに学習させるためには、リンゴのイラストを含む「正解」の画像と、リンゴのイラストを含まない「不正解」の画像両方をAIに与える必要があります。
正しい画像を抽出する作業は人間から見れば単純なミッションですが、ヒトの常識を持たないAIに「リンゴのイラスト」という定義を教え込むには相当量の教師データが求められます。
有効な教師データの量に不足があればAIがリンゴのイラストを抽出する精度は低くなってしまうのです。
実際にビジネスでの活用を想定したAIにはさらに複雑な役割が与えられますから、必要となる教師データをさらに大規模で複雑なものになり、AIに与える前にヒトが加工する必要すら生じてきます。
AIモデルを無価値なアプリケーションにしないためには、AIの基盤となる教師データをどこから・どうやって・どれくらい確保できるのかという明確な見通しを立てておくことが大切です。
おわりに
消費者として生活している中で、ここ最近はツールやサービス名に「AI」という言葉がついた表現を目にする機会が増えてきたように感じます。
AIの活用事例としてはチャットボットや画像検出などが連想できますが、広範囲の業務に活用されているAIと言われてすぐに思いつくものは無いかもしれません。
そう考えると、確かにGartnerが指摘する通り、ビジネスにおける現在のAI活用は局所的なものに留まっているのでしょう。
これまでは「日常業務から切り離された特殊な役割」程度の印象しかなかったAI開発ですが、今後はAIを如何にして業務に組み込んでいくか、どれだけ汎用性を持ったAIを開発し活用していけるかに注目が集まっていくのでしょうか。
Gartnerの予見通り、AI開発のSDGsがトレンドになるかどうか、見守ってみることにします。